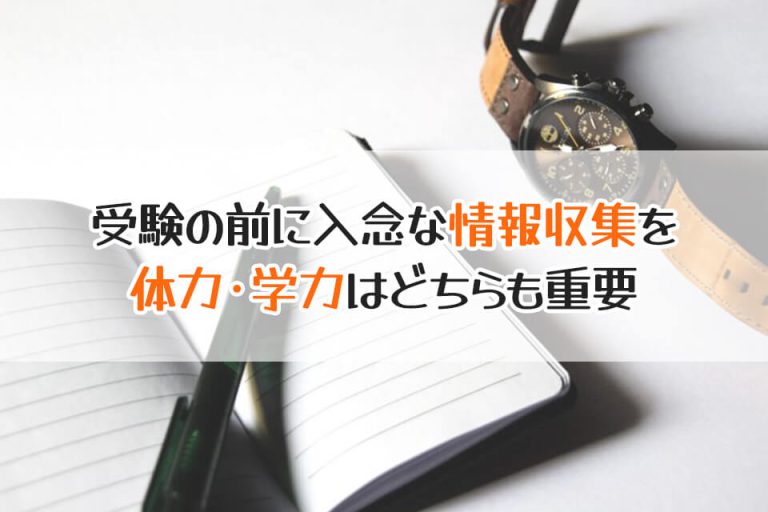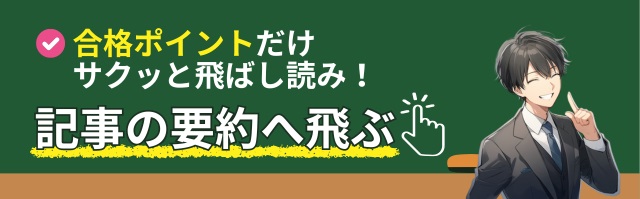「市民の生活と安全を守り、社会を支える警察官になりたい」という子どものころからの夢を叶えるため、警察官採用試験へのチャレンジを決意して、このブログにたどりついた方、当ブログはそんな方を応援するために存在しています。
合格を手に入れることは、けっして簡単ではありませんが、事前に試験の内容を把握して効率の良い対策をたてれば、夢を現実に変える道が見えてくるはず。
今回は、採用試験の受験資格や試験の内容、倍率など、事前に入手しておきたいお役立ち情報について解説します。皆さんの疑問や不安を解消して、安心して挑戦できる第一歩につながることでしょう。
警察官は国家公務員 or 地方公務員に分かれる

警察官を目指す人は、国家公務員と地方公務員の2種類の採用ルートがあることを知っておきましょう。
警察官には、以下のとおり国家公務員と地方公務員のケースがあります。
| 採用ルート | 種類 | 初任時階級 |
| 警察庁 | 国家公務員 | 警部補・巡査部長 |
| 各都道府県の警察 (※警視庁は東京都管轄) | 地方公務員 | 巡査 |
警察官の階級は、「警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査とする」と規定されています。(警察法 第62条第1項)
国家公務員として警察庁に採用されると、より高い階級からスタートできますが、採用枠が30人前後しかないため、非常に難関で狭き門です。
一方、地方公務員として地域に貢献できる現場で働く警察官を目指す場合には、次の試験(選考)を受ける必要があります。
- Ⅰ類(大学卒業程度)
- Ⅲ類(高校卒業程度)
受験できる試験(選考)は、年齢や資格によって異なるため、自分ならどちらの試験を受けられるのか、よく確認するようにしてください。
警察官採用試験の受験資格
現場での捜査実務を担当する警察官を目指す人は、国ではなく地元の都道府県警察が実施する採用試験を受けることになります。
ここでは、都道府県警察が実施する警察官採用試験の受験資格について見ていきましょう。
年齢及び学力
年齢と学力によって、I類あるいはIII類の受験資格があるかが決まります。主な受験資格は、次のとおりです。
| 分類 | 要件(警視庁警察官採用情報) |
| Ⅰ類(大学卒業程度) | ・昭和61年4月2日以降に生まれた人で大学を卒業または令和4年3月までに卒業見込みの人 ・昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人 |
| Ⅲ類(高校卒業程度) | ・昭和61年4月2日以降に生まれた人で高校を卒業又は令和4年3月までに卒業見込みの人 ・昭和61年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で高校卒業程度の学力を有する人 |
なお、短期大学ではI類の受験資格要件を満たせないので注意が必要です。
都道府県によっては、Ⅰ類・Ⅲ類の代わりに「A区分・B区分」という表記をする場合もあります。またI類とⅢ類を両方受験できないケースや、A区分に該当する人はB区分で受験できないケースなど、都道府県警察ごとに規定が異なるので見落とさないようにしましょう。
警察官の採用試験は、基本的な区分を大学卒業者とそれ以外の者に分けて、年数回実施されています。どちらの採用選考区分に申し込めるのか不明なときは、各採用センターに問い合わせるようにしてください。
身体要件
各都道府県警察の公式サイトで警察官の募集要項を見ると、身体要件を明確に提示していない場合もあります。しかし例え募集要項に記載がなくても、警察官の職務を遂行する上で支障のないレベルを求められると想定したほうが良いでしょう。
警視庁では次のとおり身体要件を明記しています。
|
検査項目 |
男性 |
女性 |
|
身長 |
約160cm以上 |
約154cm以上 |
|
体重 |
48kg以上 |
45kg以上 |
|
視力 |
裸眼視力:0.6以上(両眼) 矯正視力:1.0以上(両眼) |
|
|
色覚 |
警察官としての職務執行に支障がない |
|
|
聴力 |
警察官としての職務執行に支障がない |
|
|
疾患 |
警察官としての職務執行に支障がある疾患がない |
|
|
その他の身体の運動機能 |
警察官としての職務執行に支障がない |
|
受験資格のない人(欠格事項)
次のような人には、警察官採用試験の受験資格がありません。ほとんどの人に当てはまることはないでしょうが、欠格事項があることを念のために知っておきましょう
- 日本国籍ではない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、あるいはその執行を受けなくなるまでの人
- 当該都道府県で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
- 政府を暴力で破壊しようと主張する政党や団体を結成、あるいはこれに加入した人
- 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
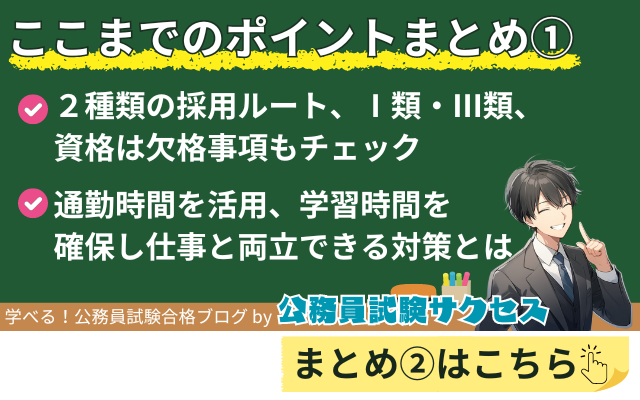
警察官採用試験の受験対策を始める方・もう始めている方にも、以下の問題集が大人気です!
↓ ↓ 送料無料!今だけ最大11%OFF!
志望自治体別・警察官採用試験問題集はショッピングサイトが断然おトク♪
☆゚+. こんな受験生が活用中 ゚+.☆
✅ 独学でコスパ良く対策したい
✅ 勉強のブランクを克服したい
✅ 仕事と両立していて時間がない
✅ 願書や面接、人物試験に自信がない
【公務員試験サクセス】
<警察官採用試験 合格体験談>
石川県 R・Hさん
通勤時間を有効活用。解法で驚きの得点ができ、合格!
私は仕事をしながらだったので、学習時間の確保と、また、最後に勉強をしていた時期からが間があったという点が気がかりでした。
しかし、公務員試験サクセスの、公務員要点解説講座と自治体別問題集のおかげで合格することができました。要点解説講座は音声講義なので、通勤時間で音声を聞きながら勉強が出来、時間を有効活用できました。解法は色んな問題で使えて、驚くほど点数が取れるようになりました。
そして、自宅では自治体別の問題集で勉強をし警察官採用試験の出題内容が分かり、要点解説講座で頻出問題を押さえていくので、必要な勉強に絞って対策が出来ました。一日、何時間勉強したかというより、今日はどの部分を勉強できたか、という量より質を重視することができました。
(大学卒業程度)Ⅰ類の採用試験の内容

地方公務員の警察官採用試験は第3次試験まで設けている場合もありますが、ほとんどのケースで第2次試験までとなっています。第2次試験が2日間に渡って実施される場合もあるなど、各都道府県警察が独自の採用活動を実施しているのが特徴です。
ここでは、受験資格が大学卒業程度とされているⅠ類の採用試験について、その内容をご紹介します。
一般教養試験(120分)
大学卒業程度の一般的知識(25問)と知能(25問)を、五肢択一式で120分で解きます。出題範囲は次のとおりです。
【知識分野】社会科学、人文科学、自然科学
【知能分野】文章理解(英語を含む)、判断推理、数的処理、資料解釈
知識分野に一般科目(国語、英語、数学)が含まれたり、知能分野に図形判断が含まれたりする場合もあります。
論文試験(60分)
「思考力、構成力等」についてみる記述式の論文試験(論作文試験)が行われます。字数は800字程度が一般的です。
試験時間が1時間20分の場合や、職務に必要な国語力のみ20分程度の記述式試験も合わせて実施される場合があります。
資格による加点制度
警察官採用試験を申し込みする際に、以下の資格を有していると申告した場合には、第1次試験では一定点が加点される場合があります。
- 体力(武道やスポーツ歴)
- 情報処理
- 語学
加点される資格の目安は、都道府県警察ごとに異なるので事前に確認しておきましょう。
人物試験(適性検査、集団・個別面接)
警察官採用試験では、体力試験、筆記試験とともに人物試験も重視されています。人物試験の内容は「適性検査(マークシート・記述式)」「面接試験(集団・個別)」など、組み合わせは都道府県によってさまざまです。
人物試験では、警察官としての適性をチェックされるので侮れません。筆記試験同様に、事前にしっかり対策するようにしましょう。
身体検査と体格検査
身体検査は、いわゆる医師による健康診断を受診することです。検査が実施される主な項目は、次のとおりです。
- 胸部疾患
- 性病等の伝染性疾患
- 痔疾
- 眼疾
- 耳鼻咽喉
- 聴力
- 血圧
- 尿
- 肝機能等
体格検査とは、先述した身体要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
体力検査
種目の組み合わせはさまざまですが、体力検査の内容はおおむね次のとおりです。
- 腕立て伏せ
- バーピーテスト
- 上体起こし
- 反復横跳び
- 上体起こし
- 握力
- 立ち幅跳び
- 20メートルシャトルラン
体力試験における種目別基準を公開している場合もあるので、事前にチェックして体力づくりの参考にすると良いでしょう。
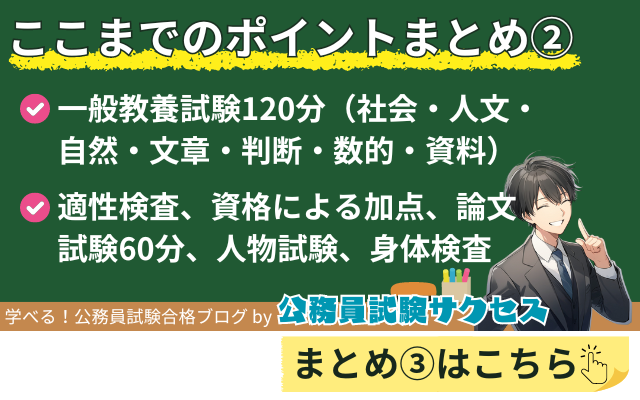
警察官採用試験の受験対策を始める方・もう始めている方にも、以下の問題集が大人気です!
↓ ↓ 送料無料!今だけ最大11%OFF!
志望自治体別・警察官採用試験問題集はショッピングサイトが断然おトク♪
☆゚+. こんな受験生が活用中 ゚+.☆
✅ 独学でコスパ良く対策したい
✅ 勉強のブランクを克服したい
✅ 仕事と両立していて時間がない
✅ 願書や面接、人物試験に自信がない
(高校卒業程度)Ⅲ類の採用試験の内容
Ⅰ類とIII類の警察官採用試験の内容は、ほとんど共通です。ただし、筆記試験において違いがあります。ここでは、警察官採用試験I類との違いを見ていきましょう。
| 試験名 | I類の試験との違い |
| 教養試験 | 知識分野の出題範囲が、I類と多少異なります。高校卒業程度の一般的知識(25問)と知能(25問)を120分で解く内容です。 【知識分野】国語、社会、数学、理科 【知能分野】文章理解(英語を含む)、判断推理、数的処理、資料解釈 |
| 作文試験 | III類では論文試験ではなく「表現力、理解力等」をみる作文試験とされています。字数は600字程度です。 |
警察官採用試験の倍率

警察官は人気の職種だと言われますが、実際に採用試験の倍率は高いのでしょうか?以下に、警視庁における男性警察官と女性警察官の合格倍率の推移をご紹介します。
| 男性警察官 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| I類 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 4.6 |
| III類 | 7.8 | 10.3 | 5.6 | 7.2 |
| 女性警察官 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| I類 | 5.7 | 7.4 | 6.2 | 5.5 |
| III類 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | 6.5 |
試験の種類や受験年度によってバラつきがあります。女性警察官の倍率が高めに推移しているのは、結婚や出産・育児などライフステージを支援する環境が整っているからかもしれません。
都道府県警察ごとに倍率は異なるので、受験しようと考えている地元警察の倍率をぜひチェックしてみてください。
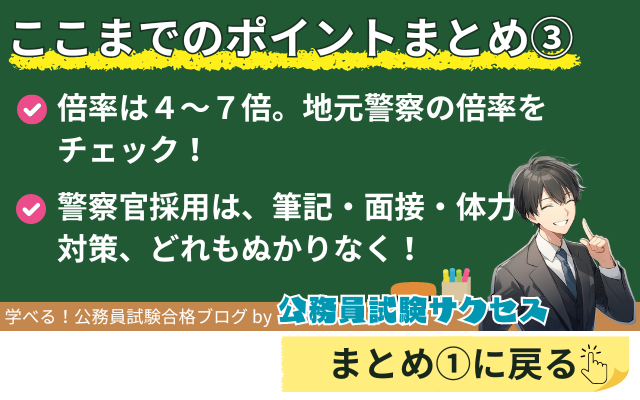
警察官採用試験の受験対策を始める方・もう始めている方にも、以下の問題集が大人気です!
↓ ↓ 送料無料!今だけ最大11%OFF!
志望自治体別・警察官採用試験問題集はショッピングサイトが断然おトク♪
☆゚+. こんな受験生が活用中 ゚+.☆
✅ 独学でコスパ良く対策したい
✅ 勉強のブランクを克服したい
✅ 仕事と両立していて時間がない
✅ 願書や面接、人物試験に自信がない
警察官採用試験合格者への通知と採用
警察官採用試験では、合格者本人に郵便で通知が行われます。警視庁の合格者への通知スケジュールは次のとおりです。
| 対象者 | 試験後の通知日 | 通知の内容 |
| 第1次試験合格者 | 約2週間後 | 第2次試験の案内 試験実施日携行品等 |
| 第2次試験合格者 | 約70日後 | 最終合格者数及び順位 |
第2次試験が終了してから、通知されるまで約2ヶ月以上かかりますので、焦らず待ちたいものです。
最終選考結果は、採用サイトに掲載されます。個人の氏名などは掲載されませんが、合格者の受験番号が発表されることを知っておきましょう。なお合格したからといって、4月1日に採用とはならない点に注意が必要です。
合格者は、警視庁警察官採用候補者名簿に登載されます。警察学校の定員などの関係で一斉に採用することは不可能なために、合格者は採用の連絡を待つことになります。
受験時に必要な持ち物(携行品)
警察官採用試験の際に、必要な持ち物とは何でしょうか?水などの飲み物や昼食はもちろんのこと、指示された携行品を忘れずに持って試験会場へ向かうことが大切です。
第1次試験の携行品の内容は、次のとおりです。
- 受験票
- 筆記用具:HBの鉛筆4本程度(シャープペンシル不可)、ボールペン、消しゴム
- マスク
- 段位等を証明する書類原本(資格加点申請者の場合など)
- 顔写真付きの身分証明書
- 昼食
警視庁の第2次試験では、次のような携行品の指示が出ていたので参考にしてください。
- 試験結果通知(第1次試験)
- 電子体温計
- 体調チェック表
- マスク
なおコロナ禍を想定した携行品は、今後の状況次第で指示の内容が変更される可能性があります。
体力検査では実際に運動をするため、汗をかくことを想定してタオルや着替えなどを準備しておくと良いでしょう。
体力だけでなく筆記試験もしっかり対策しよう
警察官になるためには、筆記試験、論文、面接、体力検査など、突破しなければならないことがたくさんありますね。体力はすぐにつくものではないので長期戦で体力づくりに取り組みたいところです。
また、試験内容を見ると教養試験や論文試験などの対策が不十分では合格は難しいと言えるでしょう。困った人を助け、地域に役立てる警察官になるには、しっかり受験準備することが欠かせません。筆記試験は勉強する範囲も広いため、自分の実力を見極めながら参考書選びを工夫するなどして全力で対策を行いましょう。