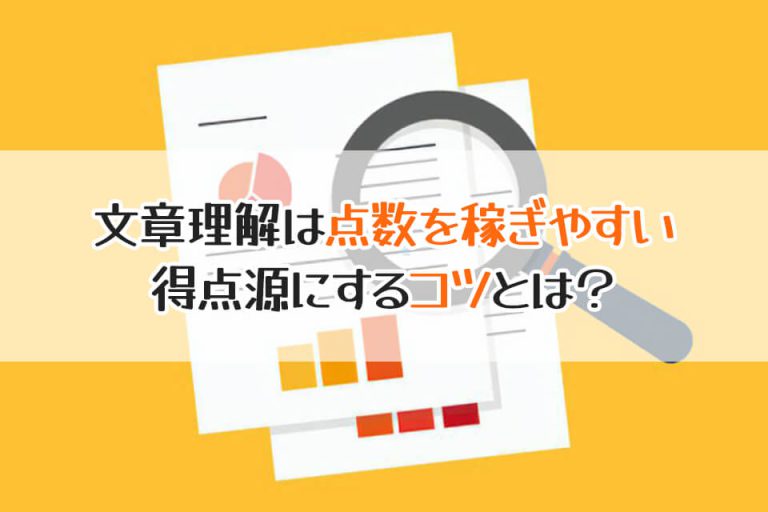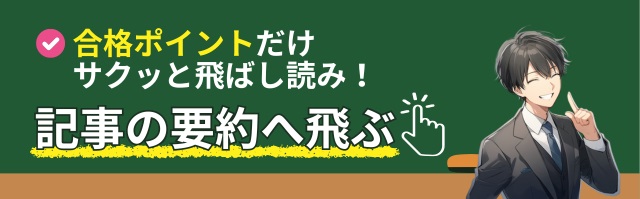教養科目の「文章理解」に苦手意識を持っている人は意外と多いです。「現代文は得意でも英語は苦手」「全くできないわけではないけど、いまいちコツを掴めず点数が伸びない」。当ブログにもこんな声がよく届いています。
逆に、小学校、環境によってはそれ以前から慣れ親しんだ教科であるため、あまり対策しないという人もいますが、文章理解は、公務員試験において数的処理に次いで問題数が多く、得点源につなげなくてはもったいない科目です。
中学や高校時代から現代文や英語が高得点だった人なら、「文章理解」にあまり時間をかけなくても済むかもしれません。ですがそうでない方は、苦手を克服して自信につなげたいところです。今回は、文章理解の1つ、「内容把握」にフォーカスし、出題傾向や対策について解説いたします。文章理解が苦手な人、確実に得点源にしたい人はぜひご覧ください。
【公務員試験サクセス】
<県庁職員採用試験・合格体験談>
要点解説講座の頻出問題は1問5分で記憶にはしっかり残って合格!
広島県 H・Aさん
「実際の問題に近い」と県庁職員の友人から聞き、公務員試験サクセスを利用しました。よくでる問題のみを集めてあるので、高得点を狙うなら要点解説講座です。
私は覚えてもすぐ忘れるので、解いたら即、復習をルールにしました。公務員サクセスの自治体別問題集を解いたら採点し、間違い箇所は、要点解説講座で解法を復習します。1問5分なので、そんなに時間をかけずにできるけれども、記憶にはしっかり残るのです。
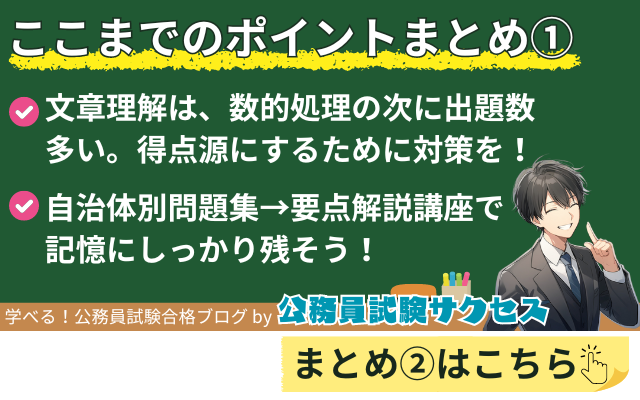

ジャンルを選択!
内容把握とは

文章理解における内容把握とは、文字通り「記された文章(本文)の内容を正確に把握できているか」という点を測るための試験です。「選択肢の中から本文の内容と一致するものを選択する」といった形での出題がおこなわれます。
内容把握の場合、本文に書いてある正解を選択肢と照らし合わせて選択すれば良いだけです。学生時代に現代文が得意だった人なら、難易度はあまり高くないと感じるかもしれません。
一方、苦手だった人は「読み解くコツが欲しい」と考えるでしょう。しかし、文章理解関係の問題は捨ててしまうには惜しい問題数が用意されています。
職種ごとに違うものの、文章理解そのものがまず非常に多い問題数です。10問前後の出題があり、40点満点の教養試験のうち、実に4分の1もの比率を占めているのです。
苦手だからと言ってこれを捨てるのはもったいないことです。
内容把握の出題傾向と得手不得手
内容把握の難易度はそこまで高くありません。センター試験を経験している人なら分かりますが、センター試験とほぼ同じくらいの難易度です。センター試験に挑める実力があれば、得点の獲得は充分に期待できます。
学生時代に国語や現代文がもともと得意だった人の中には、内容把握についてまったく対策せずに公務員試験を受けても手応えがあった、ということもあるようです。対策をしても過去問を数度解いただけであったり、他教科の勉強の合間に少し目を通すだけだったりと、苦手な人からすれば羨むような経験談が多く聞かれます。
苦手な人は「文章理解、内容把握など克服するためにはどうすればいいのか?」と考えて当然ですが、実は文章理解は短期間で知識をつけても伸びにくい性質の科目です。
もちろん無駄というわけではありませんが、知識をつけると同時に、文章を読み解くテクニックを身につける必要があります。
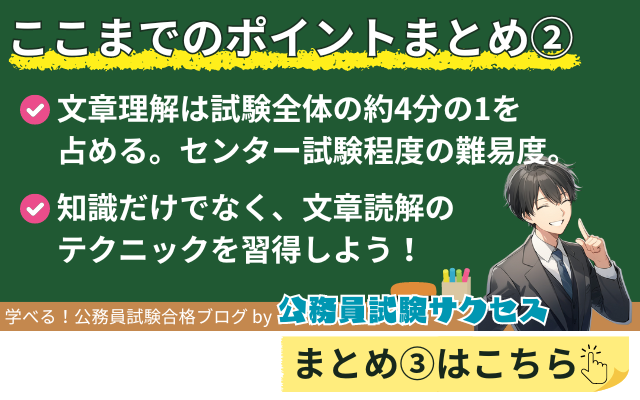

ジャンルを選択!
内容把握の対策
テクニック向上の対策の1つとしては「問題文から読む」「選択肢から読む」のどちらが自分に向いているかを分析するものがあります。ただ、これは個人によって異なります。
そこで過去問を活用しましょう。2つの方法を使って過去問を何度も解くことにより、自分に向いている方法が分かります。これは解法パターンを確立することに繋がります。
解法パターンの確立は、時間が限られている公務員試験において非常に重要です。「この問題はこのパターンで」ということが分かっていれば、効率良く問題を消化していけます。
内容把握をはじめ、公務員試験では1問に費やせる時間が長いとは言えません。1問につきおおむね3~4分で解答できなければ、時間内に全問解答することは難しいと考えられます。
内容把握の解法パターンとしては、「筆者の主張を拾い上げる」というものがあります。内容把握の問題は、ほとんどがこの筆者の主張が解答に反映されています。「筆者の主張=重要なポイント」を把握できれば、まさに内容把握ができたのも同然です。
先に問題文を読むのなら、筆者の主張らしき部分にチェックを入れておき、あとから選択肢と照らし合わせると解答範囲が絞れます。先に選択肢を読むのなら、選択肢と一致すると思われる部分にチェックをします。このとき、選択肢の文章で先入観を持たないように気をつけましょう。誤った選択肢の先入観が不正解に繋がってしまいます。
多くの問題を解いて解き方を身につけよう
文章理解の内容把握テクニックを身につけるためには、やはり問題を解くことに限ります。しかし、文章理解は短期間では伸びにくいのが事実です。
苦手な方は、当ブログが扱っている各種公務員試験の自治体別問題集を活用して、毎日少しずつでもコツコツと問題を解くことで、解法パターンを確立させてください。
公務員採用試験は、時間内に問題を解く必要がありますが、意外と「時間が足りなかった」「最後まで解けなかった」という声もよく聞きます。その原因を知らずにいつまでも苦しむ受験生は多いです。以下の記事では、時間が無くなる根本原因と、3つのコツを解説しています。問題を効率よく解ける大事なポイントが詰まっています。
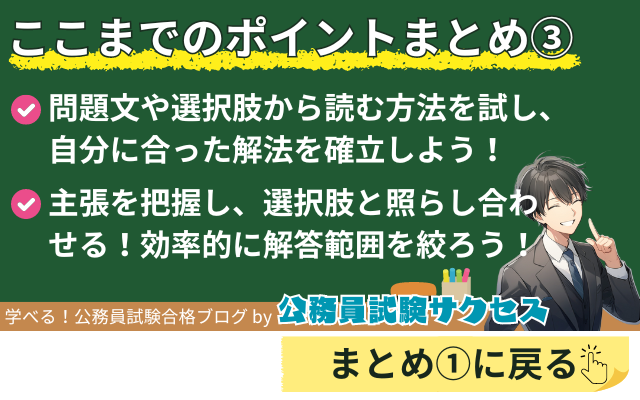

ジャンルを選択!