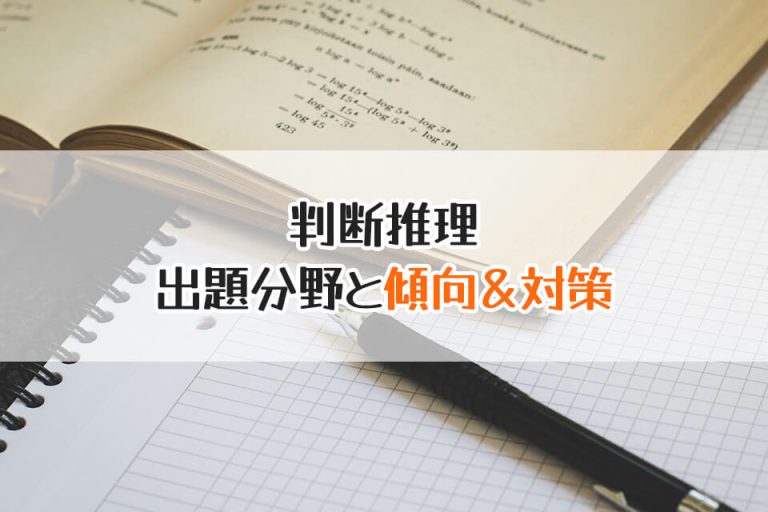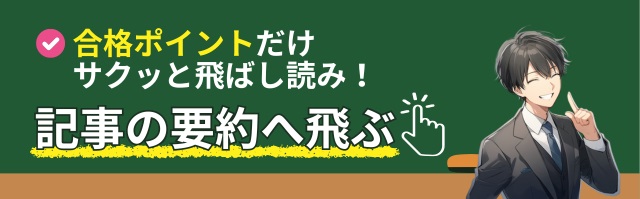公務員試験の難易度は高く、事前対策が必須の試験です。一次試験では筆記試験がおこなわれ、知識や理解力、判断力など、広い範囲で実力・ポテンシャルを求められます。
「判断推理」は筆記試験の一分野です。「一般知能」のカテゴリーにあたり、公務員に必要とされる事務処理能力が試されます。
本記事では、判断推理の特徴や出題傾向について詳しく解説いたします。公務員試験に挑まれる方はぜひ参考になさってください。
判断推理とは

判断推理とは、筆記試験の一般知能にカテゴライズされる「数的処理」のうち、全三種内の一種です。判断推理のほかには数的推理、資料解釈が設けられています。
公務員試験の中でも判断推理の得点が合格率に大きく関わると言われています。判断推理でいかに効率よく問題を解き、正答率を高めるかが重要でしょう。
判断推理は複数の条件から解答に至る問題です。問題文の中に記載されている条件を整理し、論理的思考をもって正解を導き出します。「クイズやパズルのようだ」とも言われています。
クイズやパズルのように論理的思考が求められる意味は、公務員になったとき、起こり得る問題を解決する能力があるか否かの判断のためです。
- 問題の内容を把握し、解決のための情報収集と整理
- 問題解決に有効な方法を選択・実行する
- 解決
社会に出てから問題を解決するには、このようなプロセスで進めることが多いでしょう。判断推理の問題も同様のプロセスです。
- 出題の内容を把握し、問題文の中にある条件を整理する
- 解答に有効な方法(過去問や解法パターン)を選択・実行する
- 解答を導き出す
公務員として問題解決を目指すプロセスは、判断推理の問題を解くプロセスと似ています。このプロセスは個人の論理的思考から導き出される判断能力が結果を左右する性質があり、公務員としてはもちろん、社会人として重視される能力であると言えます。
【公務員試験サクセス】
<公務員試験・合格体験談>
185の解法と自治体別問題集で、消防採用に一発合格!
三重県 Y・Wさん
消防採用に一発合格できました。公務員試験サクセスの教材と、勉強法が良かったと思います。
公務員試験サクセス自治体別問題集は解きっぱなしにせず記録をつけておくのをおすすめします。解いた日付と正解か不正解といったことを書くのです。そうすると進捗や、得意苦手の傾向が明確になるので、勉強のウェイトがつきやすく無駄な勉強をなくせます。
要点解説講座は苦手の強化にとても使いやすいので問題集との併用がお勧めです。1問5分で覚えやすく185の解法をおさえると自治体別問題集を9割解けるようになります。
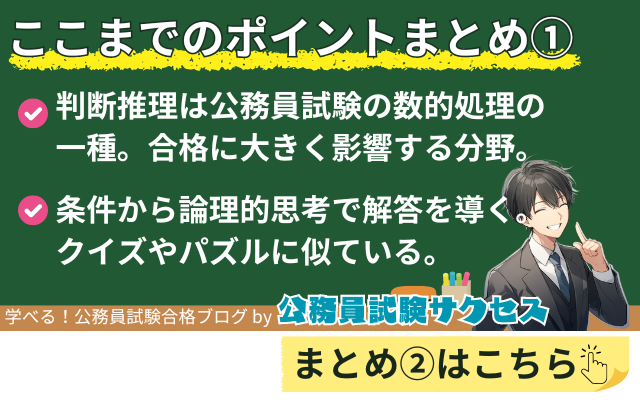
公務員採用試験の受験対策を始める方・もう始めている方にも、以下の問題集が大人気です!
↓ ↓ 送料無料!今だけ最大11%OFF!
志望自治体別・公務員採用試験問題集はショッピングサイトが断然おトク♪
☆゚+. こんな受験生が活用中 ゚+.☆
✅ 独学でコスパ良く対策したい
✅ 勉強のブランクを克服したい
✅ 仕事と両立していて時間がない
✅ 願書や面接、人物試験に自信がない
判断推理の出題分野と出題傾向
判断推理で用いられる出題分野は多岐にわたります。
「論理」「順序関係」「位置関係」「真偽(嘘つき問題)」のように論理的思考をはじめ、「立体図形」「展開図・図形の回転」など、空間把握・空間認識能力も試されます。
公務員試験における判断推理の問題の内訳は、平均として過半数が論理的思考問題です。職種によって多少の差はあるものの、論理的思考問題が多いことが分かります。
空間把握・空間認識能力問題を捨てて良いというわけではありません。
とはいえ、試験でいかに論理的思考問題が重要視されているか、ということについては分かって頂けると思います。そして採用試験で重視されるということは、公務員に求められる要素である、という証明でもあります。
判断推理の対策
公務員試験の中でも、判断推理は難易度が高くないと言われます。数的処理の中でも数学的な知識をそこまで必要とするものではなく、文系の人も苦手意識を持ちにくいためです。
判断推理は「問題がクイズのようで楽しい」と言う人もいます。得意分野だと感じられれば、重要な得点源にできるでしょう。また、苦手分野だとしても、解法パターンを掴めばその限りではありません。
ただし、難易度が高くないとはいえ、あくまでほかの分野との比較に過ぎません。一般的には公務員試験に相応しい高さであると考え、腰を据えた対策が必要です。
判断推理に有効な対策だと考えられるのは、何と言っても「解法パターンを確立する」ことです。
解法パターン、つまり「どのようなプロセスで解答を導き出すか」を身につけているか否かで、判断推理を得点源にできるかどうかが変わってくるでしょう。
「解答はできるけれど時間がかかりすぎてしまう」という傾向がある人なら尚更です。結果として解答できるからと言って、時間をかけながら漫然と過去問を繰り返しているだけでは、試験本番のときにも同様の状況に陥ってしまいます。
試験時間は限られています。筆記試験時間の120~150分の間にすべての問題を解答しなければならず、判断推理問題に時間を取られるのは大きな損失です。
試験本番で判断推理問題1問にかけられる時間は平均3~4分と言われ、あまり長いとは言えません。問題文を読んですぐに解法パターンが脳裏に浮かぶようになれば、かなりの短時間で判断推理問題を解けるはずです。
解法パターンを確立していれば、解答を導き出す時間を短縮しやすくなります。余裕をもった時間配分ができ、試験の流れに有利にはたらきます。また、素早く正確な解答により、判断推理を得点源として試験結果に反映させられるでしょう。
採用試験対策・文章理解に関しては、当ブログの「苦手でも克服できる!内容把握はテクニックで点数アップ」という記事に詳しく載っていますので、そちらも参照してください。
判断推理で点数を稼ぐコツ
公務員試験の判断推理で点数を稼ぐコツについて解説します。
判断推理は柔軟な思考力を試される問題です。以下のポイントを押さえて対策しましょう。
1.問題文の条件を整理する
問題文に与えられた条件をしっかりと読み、メモを取って整理します。 図や表を使って見える化して整理すると解きやすいです。
2.パターンを覚える
過去問や問題集を解くことで、よく出るパターンを覚えます。特に頻出問題の解法パターンを身につけると、スムーズに解答できるようになります。
当サイトでも、判断推理の再頻出問題を厳選した問題集を取り扱っていますので、ぜひご活用ください。
3.時間配分を意識する
試験時間内に全ての問題を解くためには、時間配分が重要です。特に判断推理は、一度悩んでしまうと時間があっという間に経ってしまう科目です。1分考えて分からなければ、一度違う問題から先に解くなどして、効率的に進めましょう。
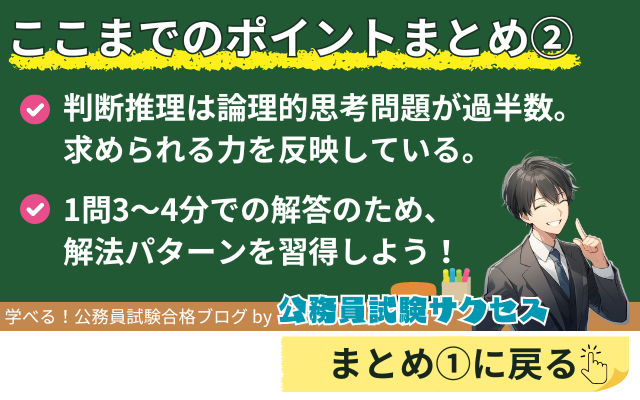
公務員採用試験の受験対策を始める方・もう始めている方にも、以下の問題集が大人気です!
↓ ↓ 送料無料!今だけ最大11%OFF!
志望自治体別・公務員採用試験問題集はショッピングサイトが断然おトク♪
☆゚+. こんな受験生が活用中 ゚+.☆
✅ 独学でコスパ良く対策したい
✅ 勉強のブランクを克服したい
✅ 仕事と両立していて時間がない
✅ 願書や面接、人物試験に自信がない
自分なりの解放パターンの確立が大事
解法パターンを確立させるまでの方法は人それぞれですが、問題と解答の暗記だけではなく、「読解」「情報整理」「トライアルアンドエラー(試行錯誤)」を重視して過去問を繰り返し解くことで、解答経験と知識を重ねることができるため、多くの人にとって有効だと考えられます。
どのような解法パターンでも構いません。問題を読んだ瞬間に「この問題はあのパターンだ」と思い付くようになれば、良い結果に反映されます。